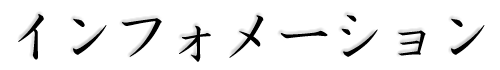本みりんには、料理をおいしく美しく仕上げるためのさまざまな調理効果があります。
今回は、本みりんの調理効果についてご紹介します。
伝統的な製法で造られた“本みりん”は、単なる甘い調味料ではありません。
その違いは「味」だけでなく、「香」「艶」「色」「形」にまで表れます。
本みりんの9つの調理効果
① あまみ
砂糖などでは得られない「上品な甘味」。奥深い甘みが特長です。
② てりつや
料理においしそうな「てり・つや」を付けます。
③ うまみ
もち米由来のアミノ酸やペプチドにより、「コクのある旨味」が出ます。
④ いろ
糖とアミノ酸が加熱されることで、きれいな焼き色に仕上がります。
⑤ かたち
アルコールと糖のはたらきにより、煮くずれを防ぎ、おいしさを逃しません。
⑥ においけし
アルコールが臭みを取り除きます。よい香りによるマスキング効果もあります。
⑦ かおり
加熱により香ばしい香りが生まれ、食欲をそそります。
⑧ あいしょう
みそ・しょうゆ・酢などの発酵調味料のかどを和らげ、お互いの良さを引き出します。
⑨ あじ
アルコールによってみりんの甘味や他の調味料の味が染み込みやすくなります。
みりんの調理効果が活きる「鶏の照り焼き」
みりんの「てり・つや・旨味・香り」が最もよく引き立つ代表的な料理が「鶏の照り焼き」。
本みりんを使うことで、つやのある美しいてりと、奥深い味わいに仕上がります。

レシピはこちら
https://kokonoe.co.jp/recipe/recipe01/recipe01-17
本みりんを用いる意義
本みりんは単なる甘い調味料ではなく、和食を支える基礎調味料です。
砂糖やみりん風調味料では再現できない、自然なてり・深い旨味・調和のとれた味わいをもたらします。本みりんの理解と使いこなしは、調理のうえで重要な要素となります。